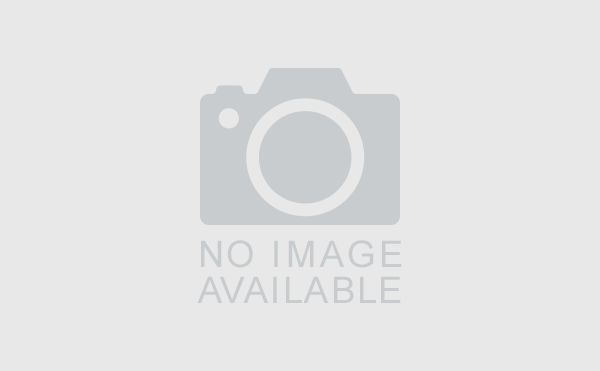相続時精算課税はギャンブルなの?
Table of Contents
相続税専門の税理士の岡田隆行(okatakatax.com)です。 ☞ 仕事を依頼する
相続時精算課税制度は捉え方によってはひとつの賭けともいえます。

相続財産に上乗せ
相続時精算課税制度は、贈与税の特例制度のひとつで、親や祖父母から財産をもらうときに使える仕組みです。
課税価格が2,500万円までの贈与は特別控除が受けられ、2,500万円を超えた分には一律20%の贈与税がかかります。2,500万円の特別控除とは別に毎年110万円の基礎控除を受けることができます。
名前のとおり生前贈与をうけてこの制度を使っていた場合、相続時に精算贈与を受けた財産は、後で贈与をした親が亡くなったときの相続財産に上乗せされ、相続税で最終的に精算されます。
上乗せされるのは、毎年110万円の基礎控除を超えた部分の金額となります。
贈与時の価格(評価額)に固定
この制度の特徴としては、相続開始時の相続財産に上乗せされる金額が、贈与を受けた時の評価額に固定されるということです。
つまり、贈与財産が贈与後から相続開始までの間に値上がりする財産であれば、相続税の課税価格は低くなります。
たとえば、今後価値の上昇が見込まれる非上場の株式(贈与時の評価額500万円)の贈与を受けておけば、相続開始時に株価が高騰(2000万円)していても、相続税の課税は贈与時の価格である500万円に固定されていますから、結果として差額の1500万円に対する相続税が安くなることになります。
逆に値下がりする財産の場合には、相続税の課税価格は高くなってしまいます。
たとえば、贈与時の評価額が2000万円の上場企業の株式の贈与を受けていたとします。
その上場企業の株式が何らかの事情で相続開始までの間に暴落してしまい、株式の価値が100万円になっていたとしても、相続時の財産に上乗せされるのは2000万円。
差額の1900万円分にかかる税金は払い損ということになってしまいますss
相続時精算関税はギャンブル
これは捉えかた、考え方の問題ではありますが、贈与後から相続開始までの間に、その財産の評価額が上昇するか、下落するか。伸るか反るか、相続時精算課税制度は一種の賭けということができます。
もちろん、精算課税制度を利用した生前贈与財産額と、相続時の財産の額をあわせても、相続税の基礎控除以下になるのであれば、精算課税制度の利用は有効です。
保険もギャンブル
保険も捉え方によっては、ひとつの賭けです。
作家の橘玲氏のことばを借りるなら保険は「不幸の宝くじ」。
保険料という名の掛け金を、保険会社という胴元に支払っておき、一定期間内に不幸にして亡くなってしまったり、ケガをしたり、病気にかかったりしたら、保険金という賞金を受取れるしくみだからです。
宝くじは当選すれば儲かりますが、その確率は極めて低く儲かることは極めて稀です。
iDeCoもギャンブル
iDeCo(個人型確定拠出年金)は、公的年金にプラスして自分で積み立てる私的年金制度です。加入は任意で、毎月の一定の掛金を自分で決めて、選んだ金融商品で運用し、60歳以降に受け取る仕組みです。
iDeCoの名称となった頃に私はこの制度に加入したのですが、税務職員の当時の同僚から「それは博打じゃないか」と 指摘されたことがあります。
iDeCoの投資対象のラインナップはローリスクな比較的安定している金融商品です。とはいえ、値下がりすることも当然ある訳ですから、博打ということばが適当かどうかはさておき一種の賭けであることは間違いありません。
相続時精算課税制度はひとつの賭けだというと、お叱りを受けそうですが、捉え方によってはそういう見方もできるというひとつの意見です。
精算課税制度を検討されている方の参考になればよいのですが。
【きょうのお仕事】
相続税申告書の提出。もちろん電子申告で。
【きょうの料理】
ナスとサツマイモと鶏ひき肉の甘酢あん。きのうはあんのトロミづけに失敗してしまい、ボソボソだったのでリベンジです。ごちそうさまでした。